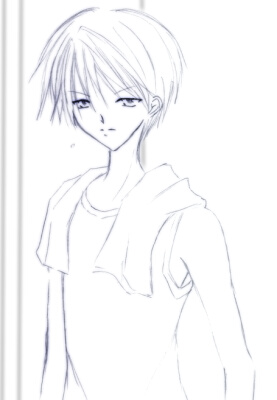011 突撃! でんじゃらす・がーる☆ 【瑞希―4】
いつだったか、名前も知らない男の先輩に校舎裏へ呼び出されたことがある。それが、どういう意味であるか、あたしでも分かっていた。
しかし、呼び出したくせに先輩はなかなか口を開かず、あたしの顔をちらっと伺っては視線を逸らして目を泳がせる。
あたしはそんなに気が長くないし、待たされることがとことんキライ。ものの数分であたしは何も言わず煮え切らない態度の先輩に向かって言ってやった。
「アンタ、男でしょ? はっきりきっぱり、ズバッと言いなさいよ!」
先輩はあたしのそんなセリフにたじろぎ、もごもごと聞き取れない何かを言った後――
「な、なんでもないです、ごめんなさい」
とだけ言って、走り去った。
相手が誰であっても、はっきりきっぱり意見を言うのがあたしだった。
だけど、彼の前だけでは違った。
――いい人に見られたい。
だけど、見せるために着飾ったあたしは、『あたし』じゃない。
ホントのあたしは……どこ?
――鎌井家、リビング。
恒くんとの会話も途切れ途切れ。この状況に耐え切れなくなっていた。
外に出たくても、右も左も分からない。帰ってこられる保証もない。リビングでじっと、おばさんたちの帰りを待つしかなかった。
ポケットに入れていた携帯がたまたま友人からのメールを受信したのをきっかけに、それをいじって時間を潰し――気付けば夕方。
テレビも地元の情報とニュースの番組に変わっていた。
その頃になって、手に荷物をたくさん持って帰ってきたおばさんとお母様は、リビングに漂うなんともいえない雰囲気にすぐ気付いた。
「……なに? この異様な雰囲気は」
「……さ、さぁ」
気にはなったみたいだけど、二人がその理由をあたしと恒くんに聞くことはなく、お父様も帰宅後すぐに気付いたみたいで、
「ただいまー。……なに? このよどんだ空気」
「さぁ……」
「留守中に何があったんだ、恒くん!!」
お父様はリビングにいた息子に尋ねる。しかし、
「べつにぃ~」
それはもう、いつもの恒くんからは予想もできなかったような、やる気のない、ぶっきらぼうな返事が吐き出された。
驚きを隠せないお父様は、放心。しばらくして、あたしに向いて聞いてきた。
「瑞希さん!!」
「いや、別に、特に何も……ね」
言えない。とても言えません。ごめんなさい、お父様。あたしはウソツキです。
またも放心するお父様。
その態度から、今までにこんなことはなかったんだろうと思う。
あたしが来て、変なことになっちゃってる。やっぱり、来ちゃいけなかったのかな? あたしが北都くんに会いたいって思ったばかりに……。
妙な沈黙を破るように、この部屋と廊下を隔てるドアが開き……北都くんが顔を出した。
「ご飯、まだ?」
お父様はキッと北都くんの方を向いた。
「北都くん、これは一体何が起こった後なんだ!!」
あまりの心配事に、お父様はいつものお父様じゃなかった。
「何がって……なぁ? オレには関係ないことだし……」
オレには関係ない――あたしの胸にぐさりと何かが突き刺さったような痛みが走った。
それから北都くんと目が合ったけどすぐに逸らし、恒くんを見た。その視線は横目で恒くんを睨むような感じにも見えた。
「ま、まぁ、思春期の子供同士のことですから、複雑なんですよ、今は」
お母様と並んでキッチンに立つおばさんがそう言ってフォロー(?)した。
確かに、複雑だった。
あたしは北都くんが好き。恒くんはあたしが好きだと言った。
じゃ……北都くんは?
恒くんの真剣な眼差しに、あたしは……。
家族揃っての夕食はとてもおいしかったんだけど、今日は楽しくなかった。
――三日目。残る時間はあと一日。
今日も朝から異様なままのスタート。
いつも一緒にラジオ体操に出掛けていた北都くんと恒くんだが、今日は恒くん一人だけが出ていた。
午前六時半。
北都くんはダイニングで朝食を取っていた。まるで、恒くんを避けるかのよう、ラジオ体操の時間に。
「明日、模試があるから、今日は邪魔しないで」
食事を早々と終えた北都くんはそういい残し、恒くんが帰ってくる前に自室へこもってしまった。
状況はサイアク。
もう、チャンスらしいものさえも残されていないようだった。
――あの時、あたしがいつものようにはっきりと言っていたら……こんなことにはならなかったのかもしれない。
後悔ばかりがあたしの思考を支配して、悪い方にしか考えられなくなっていた。
――あたしは、ここに来てはいけなかった。
昨日は疑問系だったことさえも、今日は肯定になっている。
それだけ、あたし自身も気に病んでいた。
仲良し兄弟を――あたしが壊してしまった。
ええい、うじうじ考え込むなんて、『あたし』らしくないぞ!
今日はお母様もおばさんもいるだろうし……って、何て弱気なんだろう。
「ただいま」
「あ、おかえり、恒」
お母様はラジオ体操から帰ってきた恒くんに明るく言ったけど、恒くんの様子は……昨日までのものとは違った。
あたしと目も合わさず、ダイニングの椅子に座るとテーブルに用意してある食事を口に運びはじめた。
せっかくの新しい朝も台無しになるぐらい。希望の朝は、喜びはいずこへ……。
確かにお母様とおばさんは家にいた。
しかし、陽気な話で盛り上がれるような雰囲気ではなかった。
リビングに四人もいるというのに、何? この重苦しい空気と沈黙は。
大きく溜め息までも聞こえる。あたしじゃないけど。
「宿題してくる。昼から友達んとこに行くから」
「ええ、うん」
お母様でさえ、もう対応しきれてない状態に見える。
恒くんが部屋から出ると、エアコンの効いたリビングに生ぬるい空気が少し混じった。
「……反抗期かしら?」
「反抗というか、スネてるんじゃないの?」
「何でスネてるのかしら?」
「さぁ。北都はいつも通りなのに……ねぇ」
お母様とおばさんが恒くんのことを話している。
言われてみれば、北都くんの態度には目立った変化はない。恒くんだけがあんな状態になって、あたしと話をしてくれないどころか、目も合わせようとしない。そして、北都くんを避けているようにも見える。
一人考えごとをしてると、急に肩をがしっと掴まれ向きを変えさせられた。
「昨日、何があったの? 瑞希ちゃん」
あたしに迫り、体を揺さぶるお母様。
うぁ! あたしに話の火が飛んできてしまった!!
根掘り葉掘り、昨日の出来事を聞き出され、黙っているつもりだったのに――喋ってしまいました。
だって、だって……迫り来る二人が怖かったから。
で、お昼。
まだ昼なのに疲れているあたしがいる。
お母様とおばさんは原因が明らかになって心配事がなくなったのか、陽気に会話。黙々と食べる恒くん。それを不審そうな表情で見ている北都くん。
早々と食事を終える恒くんは、すぐに出掛けて行った。
「……何だよ、なぜオレを見る」
その言葉で同じテーブルを囲んでいるお母様とおばさんを交互に見ると、二人して何だか含みのある表情で北都くんを見ていた。
「いや、だってねぇ……」
「タイミングの悪い男だと思って」
「誰が」
「……さぁねぇ~」
「ねぇ~」
「意味わかんね」
あたしにも意味が分からない。どうやら大人には結論がでたといったところか? 教えず遠まわしに言うとはズルいぞ!
「瑞希も、タイミング悪いよね~」
「あ、あたしまで!?」
おばさん、ニヤニヤしてあたしを見ないで!
昼食を終えた北都くんは、逃げるようにテーブルから去り、行き場のないあたしは――大人の餌食になっていた。
「で、北都とはどうなの?」
どうもこうも、何も起こっちゃいませんよ、見てのとおり。
「まさか、恒が割り込むとは、予想外ね」
とか言いつつ、嬉しそうですよ、お母様。
「新展開とはまさにこのことだな。はっはっは」
おばさん、笑いごとじゃないっ!!
「急展開に期待しましょう」
奥様方が大好きな昼ドラじゃないんだからぁ!! 夏休みとかはたまに見てるけど、ハラハラするのよね、うん。ちょっとエッチくて目を覆いたいシーンもあって……。
……ハラハラされてる!? あたしは昼ドラの展開に近いのか!!
果たして、瑞希はどちらを選ぶのか、明日、感動の最終回!
――他人事じゃないよ。
明日の昼には、もう……。ホントに時間がないんだから、大人たちに弄られてる場合じゃないのにー!!
だけど、明日は模試があるとかって言ってたよね? 残されたチャンスは今日だけかー!! ハードル、高すぎ。
部屋にこもっている北都くん。勉強をしているのなら邪魔はできない。
明日は模擬試験。
結局、どうにもならないことに気付いた。ここに来たタイミングの悪さにも。
まだ明るい午後六時過ぎ――友人宅へ遊びに行っていた恒くんの帰宅。
それから、お父様が仕事を終えて帰宅。
あたしにとって、鎌井家での最後の夕食が始まった、午後七時。
また明日、長旅になるということで、お風呂を早めに済ませた。
そして、就寝。
……。チャンスらしきものは、どこにもなかった。
――深夜十二時を少し過ぎた頃。
あたしはふと目を覚ました。
隣には何か訳のわからない寝言を喋ってるおばさん。
……とりあえず、トイレ。
そういえば、付き合いの悪い兄弟の代わりに大人たちのお酒に付き合わされて大量にジュースを飲まされたっけ。
それにしても、あたしって何をしにここに来たんだっけ?
溜め息をつきながら、トイレから出てドアを閉め、電気を消し、客間へ戻ろうとした時だった。
丁度、入浴を終えた直後の北都くんが、洗面所から出て、ドアを閉めている所だった。
……。
あたしにとって、これが最後のチャンス。
北都くんもあたしに気付き、見つめあうものの、言葉は出てこない。
おやすみって言ってしまったら、言われてしまったら、もう終わりだ。
正常に動いていない脳は、焦ることばかりを指示して、助言も案も出してはくれない。
これが、最後の、チャンス……なのに。
言葉は出てこなかった。
代わりに、涙が出そうだった。
――離れたくない。帰りたくない。もっと一緒にいたい。
ここに来たことで、想いが一層強くなってしまっただけ。
その想いを伝えたいのに、言葉にできないあたし。
こんなにつらいのなら、会わない方が良かったのかもしれない。そんな風にも思えてくる。
だけど、出会ってしまった。もう、後戻りはできない。なかったことにはできない。
だからせめて、この想いだけでも、あなたに伝えたい。なのに、なぜ――できないの?
「まだ起きてる?」
目が合って、北都くんがその言葉を発するまでにどれだけの時間が経ったのかはよく分からなかった。
「……うん……。ちょっと、眠れそうにない……かな」
ここで北都くんに会ってしまったから、想いが溢れそうだから、とても眠れそうにはなかった。
あたしは……北都くんが好き。だからここに来たの。
曖昧になりかけていた想いが、ここで確信に変わった。
そして、一緒にいたいとも思った。
「部屋に来る?」
あたしは即座に首を縦に振った。
神様がくれた、最後のチャンス。無駄にはしない。
北都くんはあたしの横を通り過ぎると、自分の部屋のドアを開き、その前であたしの方を見て、目で促した。
――部屋に入れ、と。
部屋の電気は点いたままだった。
初日に、ほんの少しだけ見えたシンプルな部屋は、入ってみてもシンプルなものだった。
白い壁紙の部屋――カーテンの閉まった窓際に机、入り口に近い壁側にベッド。オーディオと使用目的がイマイチ不明なデスクトップ型のパソコン。テレビはない。壁の上部にエアコン、机の横にある腰ぐらいの高さの本棚らしきものには数冊の文庫本と参考書、そしてCD。それからクローゼット。
無駄なものは何もない、という感じだ。やたらゴチャゴチャしている、あたしの部屋とは正反対。
「適当に座って」
立ったまま、部屋をぐるっと一周見ているあたしにそう言うと、北都くんは机の椅子に座って濡れた頭をタオルで乱暴に拭きはじめた。
……どうして、部屋に呼んでくれたんだろう?
そんな疑問を浮かべつつ、北都くんを見つめた。
「ん? 何?」
中途半端に濡れた髪がバクハツしているけど、それがちょっとかわいく見えた。
いや、だけど、呼んだのに、何? って言われても対応に困るのはあたしなんだけどね。
ここは笑顔でかわしてみた。
双方、話題を振ることはなく……あたしは本棚の観察をした。もしかしたら、共通の話題でも見つかるんじゃないかと思って。
文庫本……無理。参考書、もっと無理。CD……名前は知ってるけど、あたしが聴かないアーティストばかりだ。それなら聞いてみよう。話題ゲット!
「ねぇ、そこにあるCDのアーティストって、どんな感じの歌なの?」
本棚のCDが並べてある場所を指差しつつ、聞いてみた。
「どんなって……まぁ歌詞もいいし、耳にすっと入る感じがいいかな?」
聴いてみなきゃ分からないな、言われても。
「オススメの一曲とかない? 聴いてみたいな」
それが共通の話題を得る一番の近道だと、あたしは思った。
「おすすめ……っていうか、最近、よく聴くのなら――」
「それ、それでいいから、聴きたい」
あたしは何を焦っているのか、北都くんの言葉を遮ってまで言った。
「じゃ……」
机の上にあった耳に引っ掛けるタイプのイヤホンと……携帯よりも小さなもの――デジタルオーディオプレイヤーだと思われるものを手に取ると、ボタンを数回押してあたしにイヤホンを差し出してきた。
「この曲が一番好きだと思う」
イヤホンを耳に装着し終え、ベッドに縋るよう座ると、北都くんは「いい?」と聞いてきた。首を縦に振るともう一度ボタンを押し、小さなデジタルオーディオプレイヤーをあたしに手渡した。そのディスプレイには歌手名とアルバム名、曲名が表示されている。
それから、あたしは聴くことに意識を集中させた。歌詞を一句一句聞き逃さないように……。
そのメロディはテレビの歌番組やCMで耳にしたことがあった。サビの部分は思わず口ずさみたくなるような感じで……一緒に宿題をやってる時、友人が鼻歌を歌っていた。
詩は――恋愛系。それこそ、ドラマのような展開を想像させる歌詞だった。
だけど、四分ぐらいの曲の結末は……別れだった。
「すごくいい曲だよね。最後がちょっと悲しいけど」
「うん」
あたしはそのまま、流れてくる曲に耳を傾け――うっかり聴き入ってしまい、四、五曲は黙って聴いてしまった。
慌ててイヤホンを外しながら、退屈にさせてしまった北都くんに謝った。
「ご、ごめん。ついつい聴き入っちゃった」
きっと明日のために勉強でもして時間を有効に潰したと思ってたけど――北都くんはタオルを肩に掛けたまま、机に肘を突いてあたしの方を見ていた?
「えっと……」
これはどういう意味ですか?
北都くんは椅子から立つと、ちょっぴり離れたあたしの隣に座った。
「あと、この曲も結構好きかな」
とあたしが持っているデジタルオーディオプレイヤーを渡すように、手を出して促してきた。それを渡すと、ボタンを押し――流れていた曲が途中で切れ、別の曲が流れ始めた。
こちらは耳にしたことがない、初めて聴く曲。三秒程度の前奏で歌が始まる。
歌詞は……うん、また恋愛系かな。今度こそはハッピーエンドを期待してみる。
片思い、側にいるのに伝わらない、募る想い……そんな歌詞で、リズミカルなメロディ。
まるであたしの想いみたい。側にいるのに、北都くんはあたしに何も言ってくれない。
まだ、笑顔らしきものも見ていないようにも思う。
ちょっと虚しくなった。
体育座りの膝に頭をつけ、一時思考停止。
少し顔を上げると、視界が先ほどより少し暗くなっていて、誰かから顔を覗き込まれている気がした。
誰かって、一人しかいないでしょ。
寝たとでも思ったのかな?
隣から覗き込んでくる北都くんに視線だけを向けて、あたしは息をのんだ。心拍数は急上昇。心臓が頭に移動したんじゃないかと錯覚するぐらい強く打ち始めた。
な、何かヘン。
北都くん、なぜそんな顔をする。なぜ見つめる。
笑って誤魔化せる状況ではない。あたしでもそのぐらい分かる。
合った目を逸らすことぐらいしかできなかった。
「恒には……絶対に渡さない」
――はい?
音楽に混じってそんな風に聞こえたような気がした。
場違いだと思っていた北都くんの真剣な表情には、そんな意味が含まれていたことに気付く。囁くような声で、もしかしたら勘違いかもしれないけど、その言葉からは意志の強さがにじみ出ているようにも思えた。
いつもの興味なさげな表情とは違い、獲物を捕らえるような目――迫られてる!?
昼ドラは深夜に急展開って、あ~れ~。
脳内は大混乱。きゃーきゃー。
ゆっくりと、北都くんの顔が近づいていた。
ぶっ飛びましてこんばんは。真部瑞希です。
目前の北都くんの表情は、照れ混じりに変わっております。
「――っ、はぁはぁ」
わたくし、呼吸さえも忘れておりました。
心臓以外の全ての機能が一時止まってたと思われます。
感覚が戻り出したのと同時に、くちびるに余韻が残っていることにも気付く。
あたしは慌てたように手で口を覆って顔を逸らし、北都くんがいる方とは反対側の床を穴が開くほどの勢いで見た。
――な、な、何された!!
一瞬か、一分か、それとも一時間か、意識が飛んでる間に何が起こった!!
き、き、き、き……恥ずかしくて言えない!! 確か同じ名前の魚もいる。だけどとても言えない。言ったら顔の導火線に火が点いたら三秒以内に大爆発よ。そのぐらい顔が熱い。
魚も喜ぶ――あたしは動揺。
ええい、クドい。そろそろ戻ろうよ、現実へ。
北都くんの顔をまともに見ることはできなかった。
何を話したらいいのか、益々分からなくなってしまった。
ただ、黙って並んで座ってるだけ。
イヤホンからはまだ音楽が流れていた。
時間もゆっくりと流れていた。
ベッドに縋って、並んで座っていた。
……どういう意味? これ。
どうもこうも、ねぇ……あたしが勝手に思い描いていた展開に程近い状態でしょ。
っていうか、ホントにどういう意味?
「あの……北都くん、今のって……」
何かな? と言うはずが、口の中でもごもごになって、はっきり言いきれなかった。聞いてるあたしもどうかと思うが、やはり彼の口から聞きたい。
だけど、隣から伸びてくる手に気付き、怯えるあたし。肩をすくめ、身構えた。
耳に装着中のイヤホンを外され、耳に入る音らしきものはなくなり――とても、静かな空間だった。
普段は意識することのない呼吸音だけが聞こえる。そして、少し大きく吸い込まれた。
「オレは……」
言葉はそれ以上続かなかった。どれだけ待っても、出てこなかった。
あたしの胸は締め付けられるように痛む。不安になって顔を上げ、北都くんの様子を窺うと……あたしを見つめていた。辛そうで哀しそうな表情で……。
どうしてそんな顔をするの?
「オレは……」
彼は目を伏せ、あたしから顔を逸らした。
そんな北都くんが……なぜかとても愛しく思えて、あたしは彼に向かって手を伸ばし――頬にそっと触れていた。
…………。
……。
なにやってんだ、あたしは!!
引っ込めるに引っ込められない手は北都くんに触れたまま。
ゆっくりと顔を上げる彼の手が、あたしの手を包むように触れた。
目が合う。何とも言えない空気が二人の間を流れていた。だけど、イヤじゃなかった。そんな、押すことも引くこともできない、相手の気持ちが見えない曖昧さが心を振るわせる。
重ねられた手はやさしく握られて頬から離れ――空いている手はあたしの背中にそっと回され、北都くんは寄りかかるよう肩に頭を預けてきた。
ものすごく近距離。かすかに濡れている髪からはシャンプーの香り――って、パターンが逆じゃないの!
「……好きだ」
心臓の音が一層大きくなった。
今なら、素直に気持ちが伝えられる。あたしも、あなたが好きだって……。
しばらく、恥ずかしくて話なんてできなかったけど、見つめ合って、何度もキスして……ようやく会話をはじめ、気付けば三時を回っていた。
楽しくて、幸せだった時間を一気に冷ます現実――。
明日のことを考えて、あたしは客間の布団に戻った。
明日、あたしは午後二時台の電車で……。
北都くんは学校で模擬試験。
あたしたちは、明日には離れ離れになってしまう。
離れたくないのに……。